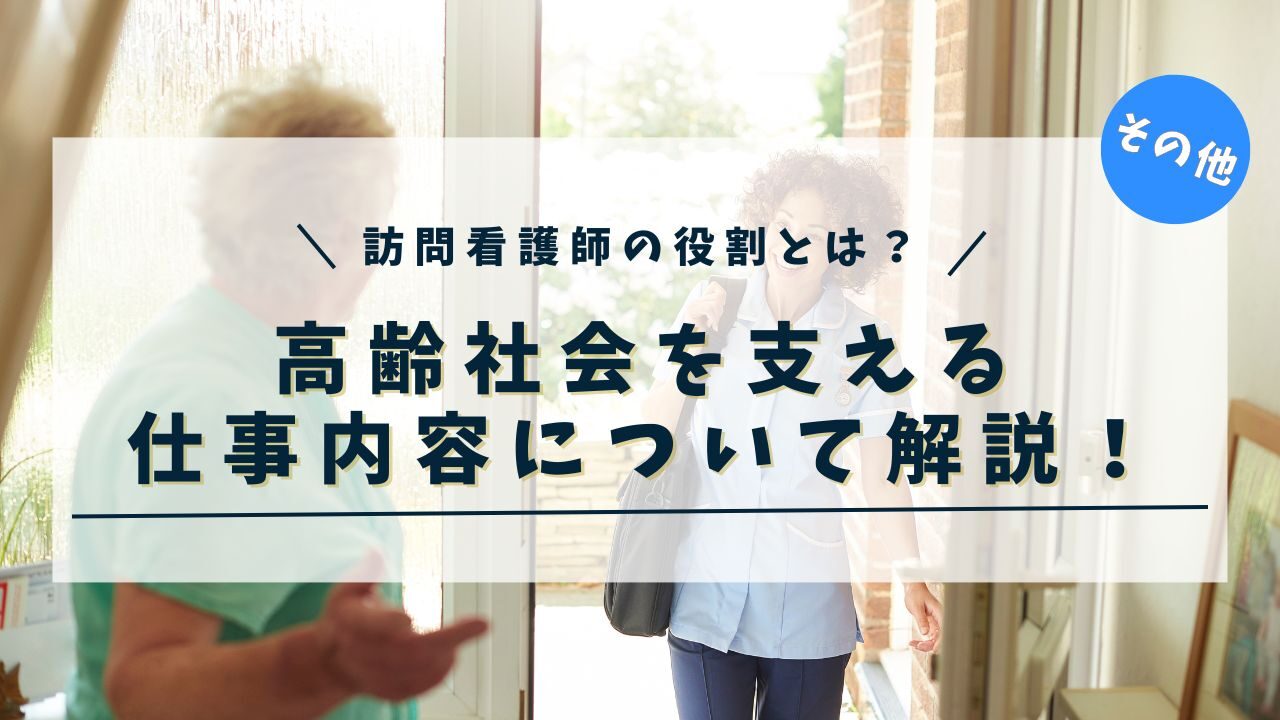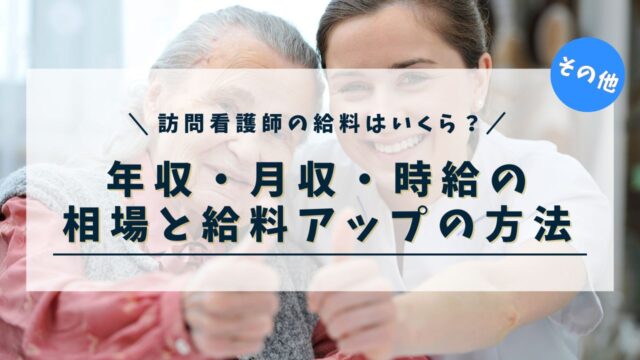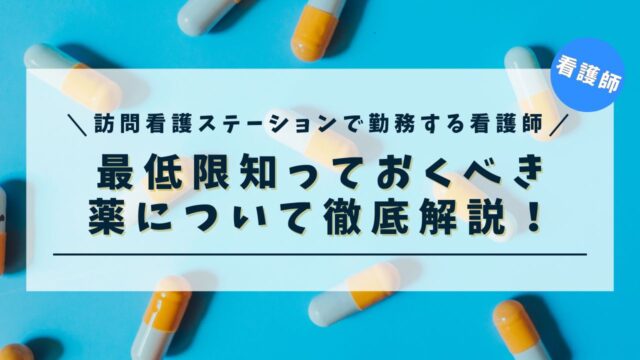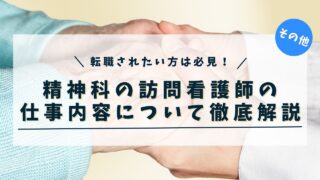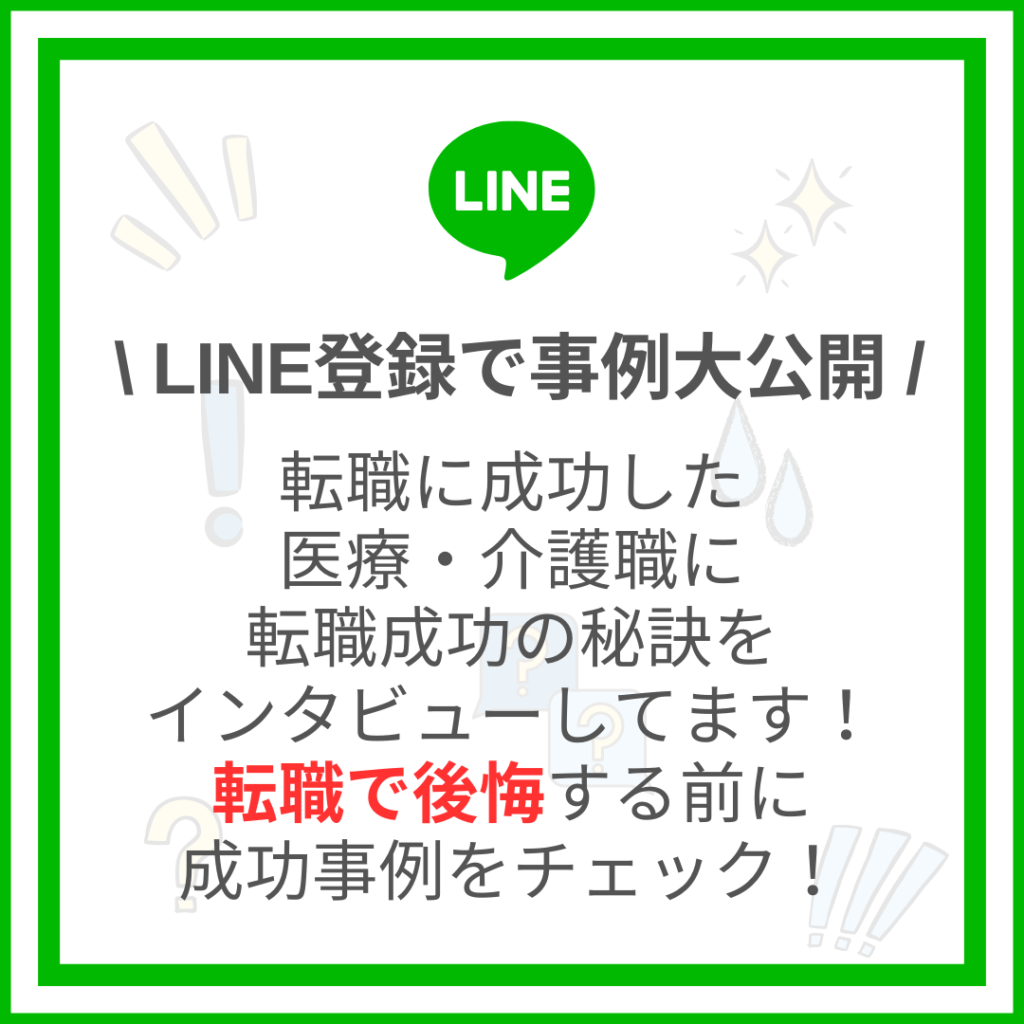高齢化社会が進むにつれて、訪問看護は在宅介護の要となっています。
訪問看護は病気や怪我や障害を持たれた方が、住み慣れた家や地域で生活を送れるように、看護師が自宅や介護施設に訪問して生活をサポートしてくれるサービスです。
訪問看護師の役割は医療と生活を支援することにあります。
この記事では訪問看護師の役割や仕事内容について詳しく解説をしていきます。
訪問看護師を目指している方は参考にしてください。
訪問看護師の主な仕事内容は?

訪問看護師が訪問先の自宅で提供する医療ケアは主に5つあります。
- 健康状態のチェック
- 自宅療養中のお世話
- 医療処置
- 状態の悪化の予防やリハビリ
- ターミナルケア
詳しく解説をしていきます。
①健康状態のチェック
利用者さんの健康状態を確認するために、バイタルサインを測定します。
バイタルサインは体温、呼吸、脈拍、血圧などで示されますが、それ以外にも身だしなみや体の健康状態などの視点からも観察します。
バイタル測定で異常と判断されれば、直ちに主治医に報告して指示を仰ぎ、医療処置を施す場合もあります。
早期の処置による対応で改善されることもあるので、健康状態のチェックは訪問看護の中でも特に重要な職務内容です。
②自宅療養中のお世話
訪問看護の仕事で、主に利用者さんから感謝される時間は生活のお世話です。
食事の介助や入浴、排泄、体位変換など日常生活の要となることの手伝いは、利用者さんにとっての不安の解消や気分転換の一環です。
ご家族以外との触れ合いを喜ばれる方もいらっしゃいますが、お世話されることが情けないと感じられる方もいるため、気遣いの心も必要です。
③医療処置
訪問看護の医療処置は、「浣腸」「褥瘡予防、処置」「経管栄養」などの処置が多くあります。
要介護度の高い利用者さんには、特に褥瘡の予防は重要です。
ご家族やヘルパーにも利用さんのポジショニングをしっかり助言し、共有認識を持ってもらうことが大切です。
④状態悪化の予防やリハビリ
利用者さんにとって大切なことは、病状や怪我の症状悪化予防やリハビリです。
例えば、褥瘡が悪化すると皮膚が壊死して傷口が広がり治りにくくなり、感染症を起こす可能性もあります。
そうならないためにも、早期に適切な処置を施し病状を悪化させない必要性があります。
リハビリは住み慣れた家で暮らすために、歩行訓練や食事動作の訓練など日常生活で必要な動作の機能回復をサポートするための支援サービスです。
⑤ターミナルケア
ターミナルケアとは、「人生の最後の時間を住み慣れた場所で迎えたい」という病状が進行した利用者さんの自宅で支援をするのも訪問看護師の役割になります。
延命治療や心身の治療行為を目的としてはしておらず、痛みの緩和や心身のケアを中心とした支援を行うことから看取りケアとも呼ばれています。
訪問看護師は利用者さんが少しでも穏やかな気持ちで、残された時間を自分らしく、家族と過ごせるようにサポートをする役割を担っています。
訪問看護と病院看護の違い

訪問看護と病院看護の違いは、「その人らしい生活」と「治療」のどちらを優先するかによって決まります。
「病気の治療を目的する場合の看護」では病院が中心の看護になりますが、「その人らしい生活」を優先したい場合は「利用者さんやご家族の意思を尊重しながら、自己決定や自立を支援する看護」が訪問看護師に求められます。
訪問看護は利用者さんの自宅に行くことが求められるためにアウェイな現場とも捉えられますが、利用者さんにとってはホームのため、個別性のある看護も求められる現場になります。
1日の訪問件数はどのくらい?

訪問看護では1日に行う訪問は4〜5件程度が一般的です。
午前中は1〜2件、午後に2〜3件というスケジュールで訪問スケジュールが組まれることが多いようです。
1件の訪問時間は30〜90分が原則となっており、60分の利用が最も多いと思われます。
介護保険の利用者さんは比較的利用時間は短く、医療保険を使われる利用者さんは長く時間を使われる傾向にあります。
また訪問看護のエリアによって訪問件数に差があります。
限られたエリアで人口が密集している都市部は、移動時間があまりかからないことから件数は多い傾向にあります。
地方の訪問看護になると移動に時間がかかり、、移動に30分以上かかるケースだと訪問件数が少なくなることもあります。
病院同様にオンコール対応も

オンコールとは利用者さんからの緊急の連絡に備えて、何かあれば直ぐに訪問できるように待機しておくことです。
オンコール対応の制度は、所属する訪問看護ステーションによって異なりますが、一般的には当番制が多いです。
オンコール当番は会社専用用の携帯電話を持ち、緊急連絡に備えて自宅で待機します。
しかし、オンコール対応といっても電話対応による相談がほとんどで、実際に緊急対応をとるケースはそれほど多くはありません。
訪問看護は事務作業も多い

訪問看護ステーションでは、月末は請求業務や報告書の事務作業が多くなります。
作成作業を5つ紹介します。
①訪問看護の作成・送付
主治医やケアマネージャーに報告する書類を作成し、利用者さんの状態を報告します。
② 訪問看護計画書の見直し
定期的に問題点や改善点を利用者さんやご家族に提案する義務があります。
③ 訪問看護指示書に期限切れがないかの確認
訪問看護指示書は最長6ヶ月間の有効期限があり、過ぎた場合は訪問を行うことができないので必ず確認をします。
④行政などへの情報提供書の作成と送付
看護師は単独では情報提供書の作成はできませんが、医師の確認や署名があれば代筆することが可能ですので手伝いをすることもあります。
⑤ 介護報酬や診療報酬の請求業務
訪問看護における請求業務とは、訪問看護のサービス料金は利用者さんに1〜3割の金額を請求し、健康保険や国民保険の適応範囲の7〜9割の金額を支払審査機関に請求する必要があります。
訪問看護ステーションでは月末から翌月初めまでは報告書や請求業務などの事務作業が多くなり、残業が発生することもあります。
訪問看護ステーションによっては、医療事務の専門スタッフが事務作業を担当する場合がありますが、医療事務が不在の事業所では看護師が作業します。
訪問看護師は高齢社会を支える大切な役割を担っている

高齢化が進む日本にとって、訪問看護は利用者さんの望む生活を支えることができる素晴らしい役割があります。
しかし、訪問看護師はそれぞれの利用者さんの家まで伺う必要があり、体力的にも負担が大きく、医療設備が整っていない場所での業務は大変です。
医療知識はもちろん、コミュニケーション能力も求められるため、病院での看護師の実務経験は必要です。
今後は更に団塊世代の高齢化が始まるため、訪問看護師の需要は高まりますが、いきなり訪問看護師になろうとすることは難しいです。
まずは、3年から5年の臨床経験を積み適切な医療処置や相談対応を行えるようになることが大切です。
利用者さんは人生の灯火が消える最後の瞬間まで、自分らしく、家族と過ごしたいと思われる方が多いです。